「スタビングトゥヴァッシュ!!」
殺女ちゃんが必殺技を放った。
複数の紅い光の球が勢いよく相川さん目掛けて飛んでいく。
紅球(こうきゅう)を自分の身に迫るギリギリまでじっと見つめてから相川さんは同じく必殺技らしきもので対抗した。
「メディスンスプラッシュ!!」
技を叫びながら注射器の押子を押すと中からピンク色の液体が勢いよく飛び出した。それは次第に発光して紅球を消しながら進んでいく。
しかし、
「駄目ね…」
ぽつりと呟いた。
紅球は発光する液体に次々と消されていたはずだったがその途中、球同士が結び合わさってひとつの大きな光の塊となったのだ。
それから液体を押し返し始めた。
再び紅球が…光の塊が彼女の身に迫る。
「どうやらここまでのよう…ね…」
「っ…!相川さん!」
どんっ!
「亜流様!?」
「亜流!?」
無意識にも私は彼女を両手で押し飛ばし、紅球から庇っていた。
そして目の前にソレは迫る。
「エレクトリックシールド!!」
すぐさま声を張り上げた。
電気を帯びたシールドが周りに現れる。
シュゥゥウ…!
紅球はシールドに当たるとまるで溶けていくかのようにして消えていった。
「ふぅ…死ぬかと思ったよ~」
「亜流様!」
安心して力を抜く私に相川さんは駆け寄ると申し訳なさそうな笑みを浮かべた。
「また…また庇われてしまいました。記憶を失ってしまわれても亜流様は亜流様のようです」
どこか懐かしいものに浸るかのようなそんな目で見つめてくる。
「相川さん…記憶を失う前の自分がどんなだったかなんて分かりませんし今、私にとって相川さんは知り合って間もない存在です。…でも、共に楽しい時間を過ごした大切な仲間だと思ってるんですよ。だからこのくらい当然です」
期待を裏切ってしまった気がして少し心苦しくなりながらもそう言って笑ってみせた。
すると彼女は今にも泣き出しそうになる。
「あ、亜流様ぁ…!!」
とうとう泣きながら抱きついてきた。
「はぁ…いい年してみっともない」
「!殺女ちゃん…」
「…殺女…」
私達の様子を見ていたのだろう。
呆れた表情をしながら屋上へと降りてきた。
相川さんは彼女をじっと睨みつけている。
「…いいわ、今回はここまでにしといてあげる」
しばらく間をおいてから諦めたように言うと殺女ちゃんはゆっくり私達の方へ近づいた。
そして目の前で足を止め…
「…なんて言うとでも思った?」
「「!?」」
嘲笑を浮かべた。
パァン!
相川さんの頬に力強くビンタする。
「相川さん!」
「っ!殺女…!!」
パァン!
今度は相川さんが殺女ちゃんの頬にビンタを返した。
「ちょっ!?ストップストップ!」
突然すぎて動揺しながらも止めようとしている私をよそに二人は再び戦闘モードに入る。
その場で叩いたり蹴ったりを繰り返す二人。
「やめてってば!!」
諦めず戦いをやめてもらおうと声を張り上げた。すると殺女ちゃんがこちらを向く。
「…亜流、物理攻撃は見ていてつまらないということかしら?」
「え?は?そういう意味じゃ…っ!?」
ヒュウウウウ!!
言い終える前に強風が巻き起こった。
見ると殺女ちゃんがまたもや宙に浮き、空の方から私達を見下ろしている。
そして彼女は相川さんに向かって再び必殺技をしかけようとする。
「スタビングトゥ……っ!?」
が。
ざわざわ…
「なんだ屋上が騒がしいぞ?」
「何が起こっているんだ!」
聞こえてきた声に慌てて屋上へ降りてきた。
どうやら病院にいた人々がただ事ではないと思い、こちらへ向かって来ているようだ。
「…亜流、病姫。普通の人間らしく振る舞ってやり過ごすわよ」
「わかった/わかったわ」
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
ガチャ!
屋上の扉が開く。
「何事…相川?」
「あ、甄(みわ)先生」
初めに清潔感を帯びた白衣を身にまとっている医師らしき男性が近づいてきた。
「騒がしい音が聞こえてきたんだが…」
「それは…その…」
相川さんが言葉に詰まる。
するとなぜか戦闘衣装を着たままの殺女ちゃんが彼女の前にずいっと出て言った。
「初めまして、歌手のAyameと申します」
「殺女ちゃん!?」
か、歌手?
普通の人間らしくとは…?
焦る私をよそに話を続ける。
「この白野病院を元気づけるため、歌を披露しにやって参りました」
「歌?披露?聞いてないが…どういうことだ?」
「彼女は私が連れてきました!Ayameの歌を聴きたいという患者さん達がいらっしゃるので」
咄嗟に笑顔で答える相川さん。
「その一人が心音さんです」
「はっ、はいぃぃ…?」
突如、名前を出されてさらに焦る。
「え、えっと…私、前々からAyameのファンなんです?相川さんが彼女の友人だと知ってどうしても会ってみたくて…あはは…はは…?」
とりあえず適当に話を繋げた。
しばらく何かを考える素振りを見せてから医師さんは言う。
「Ayame…か。聞いたことない歌手だな」
そりゃあ、歌手じゃないですから!
思わず声に出してしまいそうになりながらも必死に抑える。
当の本人は涼しい顔で嘘をつき続けた。
「最近デビューしたばかりなんです。さきほどは勝手ながら屋上で練習をさせていただいておりました。申し訳ございません」
「あぁ、それで騒がしかったんだな。納得、納得。しかし、うちはそういうのは…という以前に無断で公共施設を増してや患者がいるのにそんな風に使うとは…通報案件だぞ」
「ですよね…では────」
「あの!」
殺女ちゃんが何かを言い終える前に屋上に上がってきていた患者さんの一人がこちらに向かって声をかけてきた。
「私、彼女の歌…聴いてみたいです。普段と同じような入院生活はどうしても気が滅入って…」
それを機に患者さん達が次々と口を揃えて言う。
「俺もAyame?さんの歌聴いてみたいなぁ」
「僕も!なんだか楽しそうだし」
「こういう機会も欲しいものね」
「あ、ありがとうございますっ!?」
患者さん達に向かって一礼をする殺女ちゃん。
その表情にどことなく焦りが見えたが。
様子を見ていた医師さんは呆れ顔で口を開く。
「はぁ…お前たち、電話するからな」
え、まさか警察!?
「ちょっ────」
「上に、だ…。人並み以上に努力して真面目に働いている相川の案だ。やれしかたない」
「「「え?」」」
………………………………………………………………………………
「──────し、正気ですか?」
医師さんは電話を切るとこちらを振り返った。
「…許可がおりてしまった」
「「「えっ」」」
正直ツッコミどころしかないけれど、状況に押されたのか歌の披露…すなわちライブを受け入れて貰えてしまう。お礼を言う姉妹二人。
「「ありがとうございます!」」
「やるならこの場所で。今日一日限り。あまり大きな音は出さないようにな」
「「はい!」」
ギィー ガチャ!
患者さん達含め、人々は一旦退散した。
辺りに沈黙が訪れる。
どことなく気まずいムードだ。
「…ねぇ、殺女ちゃん」
不安を抱きながら私は彼女に声をかける。
「なによ」
「これでよかったの?」
「う…っ」
なにやら黙り込んだ。
しばらくして小さな声で呟く。
「…まさか本当に歌うことになるとは思わなかったわ」
「えぇぇぇぇえ!?」
「本来なら断られて退散する予定だったのよ!」
「ど、どうするの!?殺女ちゃん歌えるの!?」
「う、歌は得意よ!きっとなんとかなるわ!」
彼女はそう言っているけれどやはり心配だ。
ああ、この先どうすれば……
「心音さん、安心して。殺女は確かに歌は上手よ。大丈夫、大丈夫…大丈夫……」
相川さんが状況を取り繕おうとする。
しかし、彼女もまた動揺しているのかその表情に焦りが見えた。まるで自分に言い聞かせているかのように「大丈夫」を繰り返す。
「大丈夫…かなぁ?」
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
しばらくして屋上に客席が用意された。
そして歌手Ayameのライブは開かれる。
「どうも、歌手のAyameと申します。白野病院の皆様、初めまして」
「「「初めまして!」」」
自己紹介に合わせて返事をする患者さん達。
その表情は期待に満ち溢れていた。
「本日は皆様にも分かるよう有名な曲のカバーをさせて頂きたいと思っております。少しでも楽しんでいただけたら幸いです。…それでは一曲目、聴いて下さい」
「[明日のヒカリ]」
殺女ちゃんが慌てて用意したカラオケ音源のある有名曲らしいけれど私の知らない曲だ。
言えることとして曲名はまとも。あとは伴奏と歌詞と…彼女の歌唱力の問題だ。
ハラハラしながら様子を見守り続ける。
病院の放送用スピーカーから静かなピアノの音が流れてきた。
「ひとりじゃないよ そばにいるから さあ 手を繋いで~♪」
驚いた。
私が耳にしたのは穏やかなメロディー、前向きな歌詞、そしてなにより、
「一緒に向かおう~♪」
透き通った綺麗な歌声。
「ほぇぇ…」
「ね、大丈夫だったでしょ?」
後ろから肩にぽんと手を置く相川さん。
「よかったです!これでなんなく問題解決ですね!」
安心した私は笑顔で言った。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
順調にライブは進んでいき患者さん達に満足感を与えて幕を閉じた。
「お疲れ様」
事が済み、制服に戻った殺女ちゃんに相川さんが無愛想ながらペットボトルの水を渡す。
「…ありがとう」
「まさか誤魔化すだけでこうなるとは思いもしなかったよ~大成功だけどね」
私は二人の肩を寄せながら言った。
「ちょ、亜流!やめなさいうっとおしい。私達の存在が危うく世間に広まりそうになった問題は解決したけど……まだ終わっていないのよ」
「あっ…」
そういえば戦いの途中だったんだ。
恐る恐る二人を伺う。
「お二人さん?もしかしてまた戦…」
「殺女、辺りは既に暗いわ。今日はここまでにしましょう」
「はぁ…そうね。わかったわ」
よ、よかった…
……あれ?
何か大事なことを忘れているような…
「…あっ!結愛ちゃん!まだ病室で…!」
次第に不安でいっぱいになる。
「彼女の家族には連絡済みよ。もうすぐお迎えが来るはずだわ」
安心させるように微笑みながら相川さんが声をかけてくれた。
「よかったぁ…ありがとうございます」
「ふふっ本当に親友思いなのね。ただ、彼女の安否は今のところ分からないわ。気絶したまま目が覚めていないかもしれないし」
「結愛ちゃん!」
「えっ、ちょ、心音さん!?」
「亜流!?」
その言葉を聞くなり私はすぐさま病室へと急いだ。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
「ゆ、結愛ちゃん…」
「亜流ちゃん、おかえり~!」
病室に入ると私に配られるはずの夕食をもぐもぐと頬張っている結愛ちゃんがいた。
「あ!ごめんね。お腹が減っちゃってつい…」
「いいのいいの!もう全部食べちゃって!?」
悲しげな表情を浮かべるのを見て夕食を全て捧げようとした。が。
「嬉しい!…でもダメだよ。患者さんはしっかりご飯を食べないと。ちょっと結愛が食べて減っちゃったけど残りは亜流ちゃんが食べてね」
「ええ子や…」
「普通のことを言っただけだよ~?」
感動で泣いている私の頭を撫でながら結愛ちゃんはそう言った。
「ふわぁあ…結愛、なんだか疲れてるみたい」
泣き止んだのを確認するとあくびをしながら上半身をベッドに倒す。天使か…
「相川さんがお迎え呼んでくれたみたいだから安心してくつろいで?」
「知ってるよ~?目が覚めた時にテーブルの上にこれが置いてあったんだ~」
ベッド横にあるテーブルの上から一枚の紙を手に取り私に差し出す。
紙には「結愛ちゃんへ 家族にはお迎えの連絡をとってあるから安心して休んでてね 美音より」と、手書きの字で書いてあった。
「さすが相川さん準備がいい…」
あれ?でも私から聞いた訳でもないのにどうやって結愛ちゃん家の電話番号を…?
うーん…あとで聞くことにしよっと。
「ねぇ、亜流ちゃん」
「ん?なぁに、結愛ちゃん」
身体を倒した状態のまま私を見上げて結愛ちゃんは言う。
「美音ちゃんって何者なの?それに黒髪の子も…変な服装で大きな注射器とか鎌を持ってた…」
「っ!」
覚えてたんだ。
なんとなく知られてはまずいことのような気がして咄嗟に誤魔化す。
「夢じゃないかな?そんな二人見たこと──」
ガラガラッ!
「心音さん、ちょっといいかしら」
「亜流、来なさい」
突如、病室の扉が開いたかと思うと殺女ちゃんと相川さんが真剣な表情で私を呼ぶ。
「え?なんで?」
「殺女が心音さんに話があるみたいなの」
「すぐ終わるわ、だから来なさい」
ぐいっ!
「えぇ…?」
呆然として殺女ちゃんに腕を引かれるまま私はもう一度屋上へと上がった。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
「えっと…話って?」
「あなたに渡したいものがあったの」
「渡したいもの?」
「これよ!」
両手を頭上にピンと伸ばすと彼女の手元が紅色に光った。
しばらくして、その手には紫色の長剣が握られていた。
「これを私に…うわっ!?」
「今からあなたを貫くわ!」
突如、私に剣を向けながら言う殺女ちゃん。
「えぇぇええ!?」
「なんてね。冗談よ」
「びっくりしたぁ!?」
なんて心臓に悪い冗談なのだろうか。
今後一切やめていただきたい。
「亜流、あなたはこれから能力者達の暴走を止めるために彼らと戦うこととなるわ。その時、この剣はあなたの強い味方になると思うの」
「それでこれを私に…?」
刃先ではなく今度は普通に差し出された剣を手にとった。
瞬間、
ピカーッ!
「うわっ!?なに!?」
身体が桃色の光に包まれた。
そして気がついた時には、
「なんじゃこりゃ!?」
私の服が騎士みたいな…いや、魔法少女みたいな?…ともかくそんなものに変わっていた。
「もしかして私、変身した…!?」
「その通りよ。これであなたも一人前の使者ね」
肩に手を置きながら笑顔でそう言う。
一人前の…使者…
「その剣は長年あなたが使っていたものなのだけどあなたきっと剣の存在を忘れているでしょうから私が代わりに出してあげたのよ」
「ほえぇ…長年私が…」
全く覚えがない。
「これからは自分でね。使いたいと思えばいつでも出せるわ。剣を握ると戦闘衣装に変身できるの。亜流、よく似合ってるわよ」
…あれ?
なんか戦うのが楽しみになってきたかも?
「この服テンションあがるね!まさに使者って感じで!戦いたくなってきたよ~!」
「あなた本来の気持ちとしてっていうのもあるんでしょうけどその服は着ると戦いに対する意力や集中力、戦闘力、体力が上がる仕組みで作られているのよ」
「へぇー、そうなんだ」
感心しながら自分の服装や剣を眺める。
これから使者として頑張らなきゃな。
改めて思う私なのであった。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
病姫side
「大きな注射器を持ってそれで…」
「結愛ちゃん、それは夢よ」
私は困惑していた。
目の前の彼女は両腕を掴みじっと見つめてくる。どうやら殺女と戦う直前、変身した私の姿を覚えているようだった。
本来、女神特有の特別な力を使ってこの世界で騒ぎを起こしたりその事を誰かに覚えられてしまってはいけない。
あくまでこの世界を直に動かすのは人間を含む生き物達。私達、神が与えた宿命なのだ。
「亜流ちゃんも夢って言ってたけど結愛、確かに見たんだもん」
「ハッキリした夢もあるものよ」
「でも…」
自分が見た光景を事実だと言い張り、諦めない結愛ちゃん。そんな彼女に対して言った。
「もしそれが夢じゃなかったとしてあなたはどうするの?」
「え?どうもしないよ?ただ確かめたいだけなの」
「じゃあ、夢か現実かなんて知らなくても変わらないことでしょう?」
「ううん、夢だったら話しちゃうかも」
「…え?」
「夢だったとしたら結愛は友達に話すの。病院に魔女がいるって」
一体、何を言っているのだろうか。
私にはその意図が読めなかった。
「結愛ちゃん?」
「夢として誰かに話したことが本当は夢じゃなかったら…人に知られてはいけない事実だったとしたら大変でしょ?…だから知りたいの」
掴んでいた腕をぐいっと引っ張り耳元で囁く。
「夢か現実か」
「…結愛ちゃん、私は───」
ガラガラッ!
「「ただいまー!」」
病室の扉が開く。
どうやら心音さんと殺女が話し終わったみたいだ。
「おー!?二人ともそんなに近づいちゃって~仲良しさんだね」
私の肩を肘でつつきながら心音さんは言った。
「ち、違うのよ。これは…えっと…」
「えへへ、仲良しさんでしょ~?」
照れた表情を見せながら私にぎゅっと抱きつく結愛ちゃん。
「相川さんずるーい!私も結愛ちゃんとぎゅーするの!」
「はいはい、亜流と…えっと、結愛?だっけ。二人は仲良く戯れてなさい。私は病…相川美音とも話があるから。貸してもらうわよ」
「え?」
ぐいっ!
突如、殺女に腕を引っ張られる。
「「いってらっしゃーい!」」
見送りを受けながらそのまま病室を連れ出されたのだった。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
「…」
「…」
話があるとかなんとかで屋上に連れて来られたはずだけど目の前の死神は口を開かずじっと私を見つめるばかりだ。
呼んだのは彼女の方であるためこちらから口を開く気は一切無い。
よって、屋上に二人佇んでいるだけの状況が続いている。
───しばらくして。
「…病姫。あなた、私がどうしてここに来たか聞いたわよね」
殺女がやっと口を開く。
「ええ、確かに聞いたわ」
「大した話じゃないわ。亜流に剣と戦闘衣装を渡しに来ただけよ」
「本当にそれだけ?…大した話じゃなければわざわざ答える必要なんてなかったでしょう?」
私の言葉を聞いて再び黙り込む。
何かを考えるように一度何処かへ視線を逸らした後、睨みつけながら言った。
「亜流の身体がまさかあなたの元にあるだなんて思いもしなかったわ。それを知らず、この世界へ還してしまった」
「何か問題でも?」
「私は記憶を無くしている亜流にあの子が[背徳の]使者であるということを教えていないの。あなたは亜流が背徳の使者であることを知っている存在。万が一、今のあの子にそういう事を話されてしまったらなにかと都合が悪いのよ」
なるほど。
おそらく殺女は私にそういう事を心音さんに話されていないか確かめるため…そして口止めするためにこの世界に来たのだろう。
「安心しなさい。そんなことでしょうと思って亜流様…心音さんにはそういう事は一切話していないし、これから先も話す気は無いわ」
「あら、意外ね。てっきり邪魔でもしてくるかと思ったけれど」
「あくまで世界の調和のためよ。あなたのためじゃないわ。…話は済んだかしら?」
「…もう一つ」
「まだあるのね?…っ!?」
ドンッ!
私を壁に追い込んでから言う。
「何故、私と戦おうとしたのかしら?」
「……さぁ、何故でしょうね?」
思いあたるとしたら…
[共に楽しい時間を過ごした大切な仲間だと思ってるんですよ]
「心音さん達と一緒にいると温かい気持ちになるの。あなたを見た途端、それが壊されるような気がしたから…かしら」
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
亜流side
「ねー亜流ちゃーん、いつになったら結愛を離してくれるのかなー?」
「叶うならフォーエバーこのままでいよう!」
私は結愛ちゃんを長い間後ろから抱きしめ続けていた。
引き剥がすつもりなのか結愛ちゃんはぐっと力を入れてこちらを振り向こうとする。
「んー後ろが見えないよぉ…これじゃあ、亜流ちゃんの顔が見えないなぁ、さみしいなぁ」
パッ!
その言葉を聞くなりすぐさま抱きしめる手を離した。
「えへへ、ありがとう、亜流ちゃん」
「いえいえ~これで顔を見合わせられるね」
「うん!嬉しいな」
嬉しそうにしている結愛ちゃんの頭を優しく撫でる。
「ところで亜流ちゃん。あの黒髪の子、結局誰なの?」
「えっ?」
唐突に聞かれて頭を撫でる手を止めた。
「あの子はね、えっと…」
なんと答えたらいいのか分からず、言葉に詰まってしまう。
「嘘はつかないでね?親友でしょ?」
「っ!」
心に針が刺さったような感覚だった。
本当のことは言ってはならない気がする。
でも大切な親友に嘘をつくのは嫌だ。
ぐるぐると考えている内に結愛ちゃんは更に言った。
「さっきの話の続きだけど黒髪の子も美音ちゃんも変な服装で大きな注射器とか鎌を持ってた。本当に夢だったのかな…?」
ぎゅっ!
私は無意識に結愛ちゃんを抱きしめていた。
「結愛ちゃん。あの人達は悪い人達じゃないの。私の…」
「大切な人達だよ」
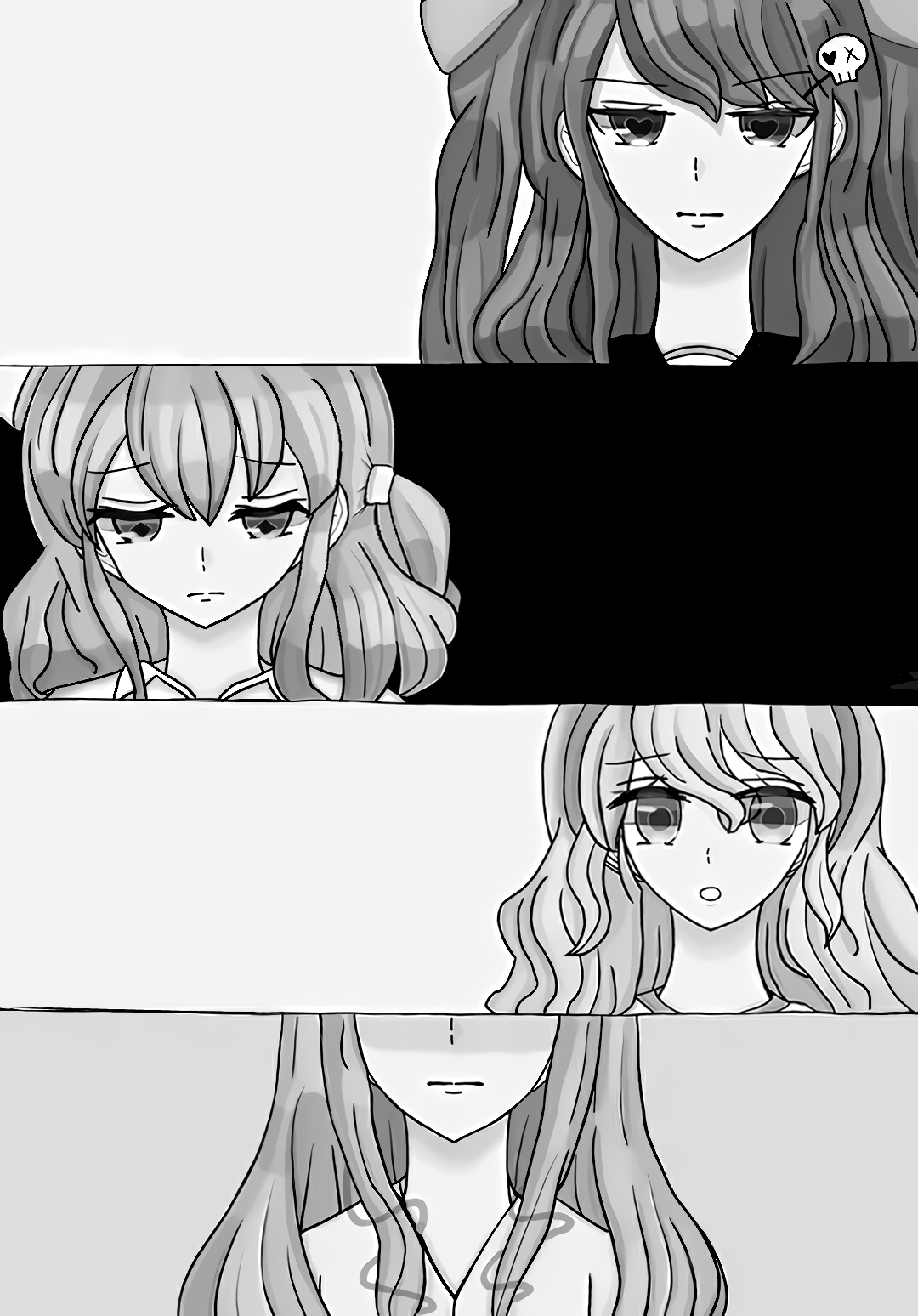
To be continued...
コメントをお書きください